��R�́@�y���̈Ӌ`
�P�D�L�^����n���
�@���̂悤�Ɍ��Ă������m���y�̉����̕��@�ƕϑJ�����A���̒��ɂ́A�������̓_�Łu�o�������v����v�f�������o�����Ƃ��ł���B�����ł́A�y���̐����ɂ܂�邢�����̎�����Ђ��Ȃ���A���y���������邱�Ƃ��ʂ����Ă����Ӌ`����_��T��A�l�X�Ȋp�x���猋�_����Ă������B
�@�܂��A�y���́u�o�������v�Ƃ��Č�����B�u�o�������v�Ƃ́A�L�����Ăъo�܂����߂̃����ɂ����Ȃ����A���́u�o�������v���̌n������A�L�^���\�ɂ��郁�f�B�A�Ƃ��ĔF�m�����ɂ�����B����y�̑����猩��A�L���Ƃ����s�ׂ́A����ȂƁA�ʂ̋Ȃ����̏�ŁA�ʁX�̂��̂ƊŘ铹��ƂȂ�A�₪�āA��������������A���ʓI�Ȃ��̂ɂ��邽�߁A�V���������Ȃǂ�t��������y��ƂȂ����B
�@�y�����ǂ߂鐹�E�҂�A�m���l�́A����Ȃ��̂��Ă݂���̂ł͂Ȃ��A�y���ɂ��邱�ƂŁA���L��ȓ`�d���\�ɂ����B���̈�Ȃ��ЂƂ̊y���ɂ���ēƗ����Ď������Ƃ������Ƃ́A�����̐��̂ɂƂ��Ĕ��ɏd�v�Ȃ��Ƃ������B�Ȃ��Ȃ�A�������e�N�X�g�Ƃ��ėp���鐹�̂́A�ʏ핶�ɂ���A�ŗL���ɂ���A����̃e�N�X�g�ɂ���Ă���B�Ⴆ�A�~�T�ʼn̂���L���G Kyrie�A�O�����A Gloria�A�N���h�[ Credo�A�T���N�g�D�X Sanctus�A�A�j���X�E�f�C Agnus Dei �ȂǂƂ��������m��48�n�ł́A�S�������̎��ɋȂ�������̂ł���A�Ȗ�������ɏ�������B�p���X�g���[�i��105�Ȃɋy�ԃ~�T�Ȃ��c���Ă��邪�A�L���G�͑S�ăL���G�ł���B�O���S���I���̂̃L���G�ƁA���ꂩ��V���I�����������[�c�@���g�̃L���G�ɂ��������Ƃ��������m��49�n �B����ɕt��������Ȃ�A�ʏ핶���܂Ƃ߂ă~�T�ȂƂ��č�Ȃ���K���́A�}�V���[�ȍ~�Ɏn�܂������̂ł���A����܂ł́A�e�Ȃ����ɍ���A���ꐫ��ێ����Ă��Ȃ������B�������������̂̐����́A�����̋L���@�̊J��̏\���Ȑ��i�͂ɂȂ����Ƃ͂����Ȃ����낤���B�����āA�L�^���ꂽ�y���́A�I���W�i���E�e�N�X�g�Ƃ��āA�V����������̎���t��������y��ƂȂ�B�I���K�k����g���[�v�X�̔��W�ߒ��ŁA�����̋L���@�̕ϑJ���݂�ꂽ���Ƃ͂��łɏq�ׂ��ʂ�ł���B
�@�����āA�L�^�ɂ́A����ɕʂ̑��ʂ�����B����́A�ۑ��̉\���ł���A���̐l�דI�Ȉӎv�𐬗����������Ƃł���B��ȉƂƂ����ɒl���鉹�y�Ƃ��A�g���o�h�D�[�� troubadour��~���l�[���K�[ Minnesanger�m��50�n�̒��ɑ��݂��Ȃ������Ƃ����A�ԈႢ�ɂȂ邾�낤���A�����̍�i�m�ɋL�^���ۑ����悤�ƍl���A��i�ɑ���n���҂Ƃ��Ă����Ƃ��Ќ������߂����̂��A�M���[���E�h�E�}�V���[ Guillaume de Machault(1300c.-1377)�ł��낤�B���m�j��----���_�A�j��Ƃ������t�ɂ́A���ꂾ���ŁA�L�^���c���Ă��邱�Ƃ���������̂���----�ł��Â���ȉƂƂ�����̂́A�}�V���[���A�Q���I�߂��O�̃m�[�g���_���y�h�̃��I�j�k�X��y���e�B�k�X�ł���B�ޓ����L�q�����B��̎����ł����l�̖������m��51�n�ɂ��Ɣޓ��́u�ō��̃I���K�j�X�^�v�u�ō��̃f�B�X�J���g�[���v�ƌĂ�Ă����Ƃ������A���̌��t�̉��߂ɂ������̖�肪����B�I���K�j�X�^�Ƃ́A�ʂ����āA�u�I���K�k����ȉƁv�Ȃ̂��A�u�I���K�k���̎�v�Ȃ̂��B���́A�ޓ��������Z�p�ɕx�u�I���K�k���̎�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ������m��52�n�Ɏ^�������A�ޓ����A�����ɂ���č��ꂽ���̂������̎�ŋL�������̂��ǂ����́A���f���Â炢�Ƃ���ł���B���݁A��ȉƂ�\�킷�p���composer�ł���A����̓��e�����componere�ɗR�����錾�t�ł���B�u��������v�Ƃ��u���ׂĂ����v�Ƃ��������t�ł���킳�����̂���ȍs�ׂȂ̂��Ƃ���A���I�j�k�X��y���e�B�k�X�̃I���K�k����f�B�X�J���g�D�X�Ƃ������y�l���́A�܂��ɁAcomponere���ꂽ���̂ł��낤�B�������A�P�����̃t�����R�́w�v�ʉ��y�_�x�̏����ɂ́A�v�ʉ��y�̕M�҂��w����notator�Ƃ������t���g���Ă���B�����ʂ�A�u�L������ҁv�ł��� notator �́A��荡���I�ȈӖ��ō�ȉƂɋ߂��B���̈Ӗ��ŁA�M���[���E�h�E�}�V���[�́A�y�����������Ƃɂ���Ď����̖����L�߁A�㐢�֎c�����Ƃ���}�����ŏ��̍�ȉƂƂ����悤�B�A���X�E�m���@�̋L���@�ɂ��c���ꂽ�y���́A��̍�ҕs���̂��̂ƁA�n�n�҃t�B���b�v�E�h�E���B�g���̂��̂������A���̂قƂ�ǂ��A�M���[���E�h�E�}�V���[�̂��̂ł���B�ނ̉��y�I�Ɛт͌����܂ł��Ȃ����A���ɁA�ނ��A��N�A�����̍�i��S�W�Ƃ��Ă܂Ƃߏグ�A���Ȏ�e�{�������Ƃ�������点�A�p�g�����Ɍ��悵���Ƃ�����������A�ނ̍�i�ɑ����ȉƂƂ��Ă̑ԓx������������B�����āA�����ŗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A���ɏq�ׂ��i�Ƃ��Ă̊y���̑��݂Ȃ̂ł���B�}�V���[�ɓT�^�I�Ȃ��̔��z�́A���y���A�y���ł����L�^�A�ۑ��ł��Ȃ��̂Ȃ�A���R���܂��ł��낤�l���ł���B��i�Ƃ��Ă̊y���̑��݂́A���Ɋւ���l�X�ȗv�f���L�q���郁�f�B�A�ł������łȂ��A���ꎩ�̂��A��̃X�e�[�^�X����тт�悤�ɂȂ�̂ł���B�����āA�A���X�E�m���@�́A���H�I�ȗ��ꂩ��L���@���J�邱�ƂŁA���̉��y���_�ɑ���D�ʐ����l�����悤�Ƃ������݂ł��������B����́A���y���A�_�w�҂�N�w�҂̂��̂ł͂Ȃ��A��ȉƂ̂��̂ł��邱�Ƃ�ł��o������̃}�j�t�F�X�g�Ƃ����߂ł���B
�@�������A�����Ƃ��������ł��낤��Ȃ̕��@�_�́A���̂��납��A�y���ɋL�q����Ƃ������@�ɏW��Ă��܂����B�ߑ�̊y�����A�C�^���A�̌��Պy�����瓾���ő�̓����́A�啈�\ great staff�ŏ������Ƃ����_�ł���B��ɏq�ׂ��Ƃ���A���m���y�́A11���I����|���t�H�j�b�N�Ȍ`�Ԃ��l�����Ă����B����ɁA�z���t�H�j�[�Ƃ������̂Ȃ�A���̗��_�͌Ñ�M���V�A�ɂ܂ők��邾�낤�B11���I�ȍ~�̐��m�̉��y�ɂ́A���m�t�H�j�[ monophony�m��53�n�́A�قƂ�ǂȂ��B�����̐��⑽���̊y�킪�v�������啈�\��K�v�Ƃ���悤�ȉ��y�́A���R�̂��ƂȂ���A�������t�ł͂Ȃ���Ȃ̕��@��v������B��ȉƂ́A�y���������Ȃ��ẮA��Ȃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł���B�������āA�y���͑n��̕K�v�����ƂȂ�B�Ȃ����Ă��A�y���������Ȃ���A��ȉƂƌĂ�Ȃ����Ƃ́A�N���V�b�N�̐��E�ł͓���O�̂��Ƃł����m��54�n�B
�@����ɁA�y���́A�ꏊ�⎞���A�P�̂ō�i�ƍl������悤�ɂȂ����B�h�C�c�̃o�b�n�́A��y�ł���C�^���A�̃r�o���f�B�̃X�R�A���w���A����Ɏ��鑽���̍�ȉƂ������A�ߋ��̃X�R�A���w�ԂƂ������@�_��z���Ă����B�y�����ǂ߂�l�ԂɂƂ��āA�y���͉��t�Ƃ̉�݂Ȃ����č�i�Ƃ��ĔF�߂���悤�ɂȂ�A�Č����ꂸ�ɁA���y���肤��悤�ȍ��o�܂ł������܂�Ă���R���ł����m��55�n�B�ł��A�ے��I�Ȃ̂́A�ޓ��̍�i�ɂ������i�ԍ��ł��낤�B�uOp.12�v�ȂǂƋL�����Op.�́A���e����Łu��i�v���Ӗ�����opus�̗��ł���B�����āA���̔ԍ��́A��ȏ��ł��A�������ł��Ȃ��A�����Ă��A�o�ŔN��ɂ���Ă�����̂ł���B
�@�����āA��ȉƈȊO���A���̍�i�����t���A�₪�āA���t�ƂƂ����E�Ƃ����Ƃ����ƁA��ȉƂ̊Ǘ����������͂Ȃ�āA��i���Č������悤�ɂȂ�B���t�������ƌ��ѕt���Ă���قǁA���Ɖ����͌��ѕt���Ă��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A���t�̏��́A�����Ƃ��Ęb����錾��̒��̈Ӗ����L����������̂ł����āA�������̂�ڂɌ�����悤�Ɏ��������̂ł͂Ȃ��B�b���ꂽ���t���ɂ��鎞�A���̘b����̐��F��C���g�l�[�V�����܂ŋL�q���邱�Ƃ͗v������Ȃ��̂����ʂł���B���ꂾ���A���t�̓R�[�h������Ă��邩��A�Ⴆ�A�����L���́A�����̉����̋L���������A����������ĕ��͂��������Ƃ������z�́A���܂�Ӗ����Ȃ��悤�Ɏv����B����A���y�ɂ́A����ȏ�̗v�����Ȃ����B��i�Ƃ��čl����Ȃ�A���|��i���A���݂���p�Ƃ��Ė{�ɂȂ�Ƃ��A�����͌��t�̑�p���ł���A�S���ς�ʈӖ������B�������A���y�̌����̗L��l���A���̂܂܈Ӗ��̕ϊ������ɁA�y���ɒ蒅����邱�Ƃ͂��肦�Ȃ��Ƃ������悤�B���܂ŁA�y���̕ϑJ�Œ��ڂ��Ă������Ƃ́A���̍����ƒ����Ƃ�����������̏��ɂ����Ȃ��B�������A�Ⴆ�A�����̃l�E�}���ɑ��݂��郍�}�k�X�����m��56�n�ƌĂ�镶���́A�L���Ƃ��Ĕ����ȃj���A���X���M���Ă��邵�A17���I�㔼�̃t�����X���y���琶�܂ꂽ�������A�A�O���}�� agrement���A���ɔ�����^����ړI�ŁA�����܂ōL���g���Ă���B
�@�����āA�ߑ�̊y���ɂ́A���t���Ȃ���ł͉��߂��Ԃɍ���Ȃ��قǑ����̃e���|�A�f���i�~�[�N Dynamik�A�ȑz expression�A�A�[�e�B�L�����[�V���� articulation�A�A�S�[�M�N Agogik�m��57�n�Ȃǂ����݂���B�y���ɂ́A���}�k�X����������ȂǁA���y�L���Ƃ��Đ������Ă�����̂����邪�A�����̌`�Ԃł͂Ȃ��A�����Ƃ��Ďw������鉹�y�I����������܂��̂悤�ɓ��݂��Ă���B�������A�����́A��ȉƂ��n�������ʂ�ɉ��t�������邽�߂ɂ́A�K�v�s���Ȃ��Ƃł���ƍl������B�y���́u�o�������v�ł͂Ȃ��A�ڍׂȕ��͂Ɖ��߂�K�v�Ƃ��鐸���ȃ��f�B�A�ɂȂ��Ă��܂����B�������Ȃ���A��ȉƂ��ǂ�ȂɏڍׂɊy�����������߂Ă��A�����Ĕނ̎v���Ƃ���ɍČ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�G�N�g�[���E�x�����I�[�Y Hector Louis Berlioz (1803-1869) �̏ڍׂȕ\��ɂ���āA�܂�A���ۋL���ł͂Ȃ�����Ƃ��Č��ꂽ�y�����A���[�c�@���g�̂������ăV���v���Ȋy�����A�y���Ƃ��ĕ��ʑ�ɂ̂����鎞�A���t�Ƃ̑O�ł͓����ƂȂ邾�낤�B�����āA�y���̕s���S�Č����������A���t�Ƃ̃X�e�[�^�X��z���ŏ��̏����Ȃ̂ł���B�����āA���̂��Ƃ���ԗǂ��m�邩�炱���A��ȉƂ́A�L����ɐV���ȋL�q��t�����Ă����̂ł���B���̋L�q�̖��͍ĂтƂ肠���邪�A����Ɍ������A������������A����͂��Ȃ��B
�Q�D�y���ɂ�鉹�y�̊g��
�@���̍����A���̒����Ƃ�����̗v�f���u�����v���邱�Ƃɐ��������y���́A��ԂƎ��Ԃ̃V���{�����ɁA���ꕽ�ʏ�ɖ��������B��̃��f�B�A�ł���݂̂Ȃ炸�A���j��A�n�߂đn�����ꂽ���Ԃ��v������V���{���ł������B�y���ɂ������ԓI�ȃV���{�����A��r�I�����i�K�ɐ������A���ԓI�ȃV���{�����A�������y�̔��W�𐄐i�͂Ƃ��Ă悤�₭13���I�ɂ͂���A�m������邱�Ƃ͑O�ɏq�ׂ��ʂ肾���A�����̃V���{���𐳊m�ɕߑ��ł���悤�ɂȂ�ƁA���m�̉��y�Ƃ́A���y�̃V���{���ɂ��^����e�ՂɊg�傳���邱�Ƃ��\�ɂȂ�B����́A��̉���n�܂�A����Ȍ`���m��58�n�ւƍL�����Ă����̂����A�����̌`�������ꂽ���y�́A�قƂ�ǁA���m�Ǝ��̋@�\�a���@�ɂ��Ƃ��낪�傫���B
�@���m�t�H�j�[�ł���A�|���t�H�j�[�ł���A���邢�́A���m�ȊO�̉��y�ɂ��قƂ�ǂ̏ꍇ�ŋ��ʂ���̂����A���y�ɂ́A���S���ւ̒������Ƃ������������݂��Ă���B�ȒP�Ɍ����A�u�h�v�𒆐S���Ƃ��Ďn�܂�������́u�h�v�ɉ�A���I��Ƃ������Ƃł���B�^���Ƃ������̂́A�����I�Ȃ��̂ł���A�V���{����̂��̂ł���A�I�n�ւƌ�������A�̓����ł���Ƃ����x�z�I�ȍl�������A���̏ꍇ�ɂ����Ă͂܂�悤���B���̒��S���̎����͂́A���ɁA�y���������m���y�̏ꍇ�A�ۂ������͂����ɂ�����B���̂��Ƃ́A�u���y�Ƃ����̂́A�Î~�Ƃ������錈�܂����_�Ɍ������Ď��������A�̃C���p���X�ɑ��Ȃ�Ȃ��v�m��59�n�Ƃ�����ȉƃC�S�[���E�X�g�����B���X�L�[ Igor Stravinsky (1822-1971)�̌��t�ɂ悭������Ă���B�|���t�H�j�[���y���A���l�T���X��ʂ��ĉ�������Ƃ������闲�����}���A17���I�O������A���m�̉��y�̒��S���z���t�H�j�[�ւƈڍs���Ă��������Ƃ͂��łɏq�ׂ��B�z���t�H�j�[�́A1750�N�������ɂ͂��܂�ÓT�h�E���}���h�̎���ɁA���������������B��X���A���ʃN���V�b�N���y�ƌĂсA�������Ă��鉹�y�́A�܂��ɁA���̎���̉��y�ł���B���̉�X��������N���V�b�N�I�Ȃ��̂����A���̒��S���̈��͂ł���A����̓z���t�H�j�[�ɂ����Ă����Ƃ������������鐫���������Ă���B�����ȒP�ɁA��قǂ́u�h�v�ɉ�A���鉹�y�ōl����ƁA�Ⴆ�A�P���̉���ɂ����ẮA���S���u�h�v�Ɍ������u�V���h�v��u�����h�v�Ƃ��������͈͂�ł���B�|���t�H�j�[�ɂ����ẮA�����̈��͂́A�������Ɨ����Ă��邽�߂��ɋN����B����ɑ��A�z���t�H�j�[�́A�����̈��͂��a���Ƃ�����̉��������̉�̒��ŁA��ĂɋN����B���S���̑��ɁA���a���Ƃ������t���A���͂Ȉ��͂������S�a���ƂȂ�A���̑��̕s���a���m��60�n�́A�S�āA���a���Ɍ������Ď�������B�I�n�̐��i�������Ȃ�����a���͏�ɁA���I�ŁA�ْ���s����������炷�B�܂�A����炪�����ɋN����z���t�H�j�[�̕����A�ْ���s���肩��̏I���ւ̊��҂���苭�܂�Ƃ������Ƃł���B
�@�����̘a���̐����𗝘_�������̂́A�t�����X�̌���o���b�N���\�����ȉƃW����=�t�B���b�v�E�����[Jean-Philippe Rameau(1683-1764)�ł���B1722�N�A�ނ̒��킵���w�a���_ Trait� de l'harmonie�x�́A���̌�́A���m���y�̐��藧���Ɍ���I�Ȍ��͂����邱�ƂɂȂ�B�y���̐��E�ŁA�@�\�a�� functional harmony �ƌĂ��A���ꂼ��̘a���������K�肷���ŁA�ǂ̂悤�Ȗ������ʂ����A������Ă����̂��͂��邱�̗��_�ɂ��ƁA�a���́A�ŏI�I�ɁA���S���̋@�\������a���Ɍ������ĘA������A�I�n�` cadence���`������B�������y�ƌĂ��S�Ă̂��̂��A�ǂ�Ȃɓ]�����J��Ԃ��A���G�Ȑ�����Y���������Ă����Ƃ��Ă��A�a���I�ɂ́A�S�āA���̋K���ɂ���Ă���B�ʑt�ቹ�ɂ�����a���̗��L�@�́A���̗��_�ɉ��p����A19���I�Ƀt�[�S�E���[�}�� Hugo Riemann (1849-1919)�̋@�\���_�ŁA��̒��_�ɒB�����B���m���y�̑b�ƂȂ�A���x�ɓW�J����Ă����a�����_���x������̂��A���ϗ��Ƌߑ㕈�@�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�I���Ɍ������Ă�������A���y�́A������ł����������邱�Ƃ��o����B�a���@�ɂ��]����A�ϑt���J��Ԃ��Ă������Ƃ��ł��邾�낤�B�y���Ƃ����V���{�����A���Ԃ̗����\�L���A���G�Œ���ȍ�i�ނ��Ƃ��\�Ƃ���̂͌����܂ł��Ȃ��B�����āA���̂悤�ɕ��G�Œ���ȉ��y�̗���͂₪�āA�X�^�C���Ƃ��ẴR�[�h���l������悤�ɂȂ�B���y�ɂ����Č`���ƌĂ����́A���邢�͊y���_�Ƃ��Ę_��������̂�����ł���B�\�i�^�`���́A�܂��A���̃\�i�^�̏������咲�ŁA���̎�肪���t�����B�㑱�̑��̎��́A���̃\�i�^���A�����̏ꍇ�́A�����ցA�Z���̏ꍇ�͕��s���֓]�������m��61�n�B���̒��ƌĂ�镔���͂����Ă��J��Ԃ���A���ɕs����ŁA���I�ȓW�J�����͂��܂�B�₦�ԂȂ��]�����J��Ԃ���Ȃ���A���y�͐i�݁A�Č����ɓ���B�Č����́A���ƂقƂ�Ǖς�Ȃ����A���̎��ֈڍs����ۂ̓]���͂Ȃ��Ȃ�B�����āA�R�[�_�ƌĂ��I�������������ƂɂȂ�B���̂悤�ȉ��y�`����g�ݗ��Ă���w��ɂ́A�y���̑��݂��s���ł���B�����I�ȗ���Ƃ��āA��̉�����A����A�����ĉ��y�`���ɂ�����X�^�C���Ƃ��Ă̎��Ԃ̊l�����y�����A��ԂƓ����Ɏ��Ԃ��V���{�������Ă��邩��\�Ȃ̂ł͂Ȃ��낤���B�nj��y�Ȃ̍ł���K�͂Ȃ��̂ł�������Ȃ́A���̑��y�͂ɂ��̃\�i�^�`���������A���ɎO�̊y�͂����B���̂悤�ȋK�͂ƕ��G���̊l���ɁA�y�����s���ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�R�D�y���ɂ�鉹�̃R�[�h��
�@���m�̉��y�j���A��Ȃ��ꂽ���y�̗��j�ł���Ȃ�A���܂܂ł݂Ă������̂́A�u�K�͓I�v�Ȋy���̗��j�Ƃ������ƂɂȂ邩������Ȃ��B�������A���́u�K�͓I�v�u�L�q�I�v�Ƃ����敪���A���y�I�ɂ͕ٕʂ��ɂ������̂ƂȂ��Ă���B���y�l�ފw�̃t�B�[���h���[�N�Ȃ�\��Ȃ����A��Ȃ̂ǂ��܂ł��A�u�K�͓I�v�ł���A�ǂ�������u�L�q�I�v�ƊŘ��́A���܂�Ӗ��̂Ȃ����ƂɎv����B�Ȃ��Ȃ�A�u�L�q�I�v�y�����A����Ӗ��A�y���̎��L�q�������y�̒��ɊҌ����Ă�������ł���B�V������ȕ��@�̊J��Ƃ��Ăł͂��邪�A�y�������y�̋L�^�ɂł͂Ȃ��A���̎��ۂ������鉹�̋L�^�Ƃ��Ďg������ȉƂ���������B���̐��ɍ���D��ꂽ��ȉƂ͑����B���ɁA������u���Y���Ƃł���A���ފw�҂ł���v�ƌ����I�����B�G�E���V�A�� Olivier Messiaen(1908-1992)�́A���E�e�n�̒��̐����̕����A��i�Ɏ�����Ă���B���ł��A�s���̃J�^���OCatalogue d'oiseaux�t(1956-58)�́A���t���Ԃɂ��ĂR���Ԕ��ɂ���ԃs�A�m�Ȃ����A���̑S�҂����̉̂����ō\������Ă���B�l�̉�b���y���ɋL�q�����̂́A���I�V���E���i�[�`�F�N Leos Janacek(1854-1928)�����ł͂Ȃ����낤�B�ޓ��́A�����̃��`�[�t�����y�ɓ����������A���̂悤�ȁA�\���邱�ƂŁA�u�K�͓I�v�Ɓu�L�q�I�v�̋��E���j�ꂽ���Ƃ�Q�������A�y�����A���y�≹���̂��̂����R�ɕϒ����������y�Ƃɗ^�������Ƃ�]�����ׂ���������Ȃ��B���̐��͎��R�Ɉڒ�����A��b�͒f�Љ������B���y��i���̂��A���̑f�ނƂȂ肤��B�x�[���E�o���g�[�NBela Bartok (1881-1945)�Ȃǖ������y���̕����A�����̍�i�ɓ���������ȉƂ͑������A�L�q���Ƃ����Ӗ��ŁA�R�s�[����p�Ƃ��������w�I���@�����邱�Ƃ��A���R�\�ɂȂ����B���`�A�[�m�E�x���I Luciano Berio(1925-)�́s�V���t�H�j�A Sinfonia�t(1968)�̑�O���ł́A�}�[���[�́s�����ȑ��ԁg�����h�t(1888-1894)�̑�R�y�͂̊��S�ȍČ���y��Ƀo�b�n����A�V���g�b�N�n�E�[���m��62�n�ɂ�����ߋ��̍�i�̉��f�ނ����R�Ɉ��p�����B���p�́A���R�A�ߋ��̉��t�ɂ��̂ł͂Ȃ��A�L�^���ꂽ�y���ɂ��̃I���W�i�������߂邾�낤�B����ɁA�X�e�B�[���E���C�qSteve Reich(1936-)�̂悤�ȍ�ȉƂ́A�������������@�ɁA�R���s���[�^�[�������B�ނ́s�P�C�� Cave�t(1993)�ɂ����āA�C���^�r���[������ꂽ�l�̌��t���A��U�R���s���[�^�[�ŁA�����A������y���ɂ��������A���̊y��ɕϊ����āA���t����Ƃ����Z�@���g�p�����B�����̂��Ƃ́A�y�����A�n�삳��鉹�̘A�Ȃ�ȊO�̂����鉹�f�ނ��A�ϒ����A�ϊ����A�f�Љ��ł���f�W�^���I�ȃR�[�h�Ƃ��Ă��������邱�Ƃ������Ă���B
�@�����悤�ɁA�����̕\�����\�ɂ������ƂŁA�y���́A���Ԃ̃R�[�h�������\�ɂ����B�Q�[�U�E�T���V�́A�������y���ߑ�Ȋw�̐��݂̐e�ƕ߂����_���������Ă��邪�A���l�T���X�̉�Ƃ������A��Ԃ�䗦�Ƃ��Čv�����铧���}�@�ݏo����葁���A�������y�̉��y�Ƃ����́A���Ԃ��V���{�������邱�Ƃɐ������Ă���_�����m��63�n�B���̃R�[�h�����ꂽ���Ԃ��A���R�A�y���̏�ŁA�l�X�ȕϊ��������邱�ƂɂȂ�B�܂��A�I���K�k�����s�O���S���I���́t�̋�ԓI�g�傾�������Ƃ͑O�q�������A���ԓI�g���ڎw�����z����i����́A�V���ɍ��킹���Ԃ����邱�Ƃ����̖ړI�ł������낤�j�A�e���ɂ���т₩�ȑ��������A�����ꉹ�ʼn̂������X�}��A���̃����X�}�ɐV���ȉ̎������̂��g���[�v�X�Ƃ����`�����a�������B�J�m���Ƃ������y�`���́A��s���鐺�������鎞�ԊԊu�������Č㑱�������A�ǖ͕킷��B�g��J�m����k���J�m���ƌĂ��`�Ԃł́A��s�����̉������A���{���A���邢�͉����̈ꂩ�ɐL�k����Ė͕킪�N���邵�A�t�s�J�m���ł́A��s�������A�������玞�Ԃ�k��悤�ɁA�͕킳��Ă����B���̎��Ԃ̐L�k���������Ƃ��[�I�Ɏ����̂��A�������(1929-)�̃g�|���W�B�E�ʑ��w���Ƃ肢�ꂽ�t���[���ɂ���ȕ��@�ł���B���߂��t���[���Ƃ���0����12�̐��ɓ���������B�y���́A���łɎ��ԓI�����\����L���Ă���̂�����A�����ɁA�������ق����A�Ȃ�ׂ���B�Ƃ��낪�A��ꐺ���Ƒ���ɁA�ʂ̃t���[����������邱�Ƃɂ���āA��ꐺ���������A���̂܂ܖ͕킷�鏃���ȃJ�m����������Ƃ��Ă��A��s�������A���������葁���A��������̖͕������Ƃ���������������̂ł����i����3-1�j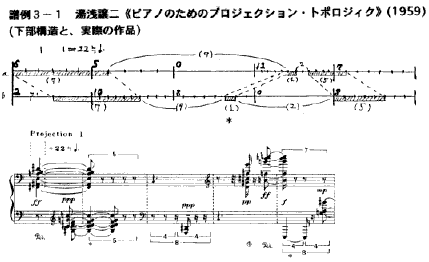 �B���Ԃ��t���[���Ƃ��ăR�[�h�����邱�ƂŁA���̂悤�ȃS���̂悤�ȐL�k���鎞�Ԃ��A�V���{���Ƃ��đ��݂��A���t�ɂ���ċ���ł���̂ł���B�~�j�}���E�~���[�W�b�N�ƌĂ�鉹�y�̑�\�I�ȋZ�@�́A�u�Q���ړ�����v���Z�X�Ƃ��Ẳ��y�v���Ȃ킿�A�u�Y���v�ł���B���C�q�́s�s�A�m�E�t�F�C�Y Piano Phase�t(1967)�ł́A��l�̃s�A�j�X�g���A�܂������������t������̂����A��l�́A����������ɑ����e���|���ݒ肳���B�����ɂ́A�قȂ�����̎��Ԏ������܂�邱�ƂɂȂ�B�|���t�H�j�[�́A�����̋L���@���A���A�|���N���j�V�e�B�Ƃ������鑽�w�I���Ԃ��A�����A�L���@�������ē�����悤�ɂȂ����̂ł���B
�B���Ԃ��t���[���Ƃ��ăR�[�h�����邱�ƂŁA���̂悤�ȃS���̂悤�ȐL�k���鎞�Ԃ��A�V���{���Ƃ��đ��݂��A���t�ɂ���ċ���ł���̂ł���B�~�j�}���E�~���[�W�b�N�ƌĂ�鉹�y�̑�\�I�ȋZ�@�́A�u�Q���ړ�����v���Z�X�Ƃ��Ẳ��y�v���Ȃ킿�A�u�Y���v�ł���B���C�q�́s�s�A�m�E�t�F�C�Y Piano Phase�t(1967)�ł́A��l�̃s�A�j�X�g���A�܂������������t������̂����A��l�́A����������ɑ����e���|���ݒ肳���B�����ɂ́A�قȂ�����̎��Ԏ������܂�邱�ƂɂȂ�B�|���t�H�j�[�́A�����̋L���@���A���A�|���N���j�V�e�B�Ƃ������鑽�w�I���Ԃ��A�����A�L���@�������ē�����悤�ɂȂ����̂ł���B
��R�́A����